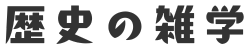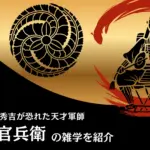斎藤道三は戦国時代に美濃国(岐阜県)を中心に活躍した大名です。
知略と策略に優れ「美濃のマムシ」と恐れられました。
娘を織田信長に嫁がせるなど、織田信長とも深い繋がりがあります。
この記事では
- 斎藤道三が戦国大名になるまでのエピソード
- 斎藤道三と織田信長の関係
- 斎藤道三の年表
などの雑学を歴史初心者にもわかりやすく紹介します。
※諸説あるものや逸話が含まれます。
斎藤道三の雑学
出自の謎
道三の出自については、いくつかの説があります。
近年一番有力なのは油売りから身を興したというものです。
油売りであった父・松波庄五郎が美濃守護土岐家の家臣となり、その地位を道三が継承したとする説が有力視されています。
他にも、代々北面武士(御所の警備にあたった武士のこと)を務める武家の子として山城国(京都府南部)で生まれたとする説もあります。
また、若い頃は京都の妙覚寺で僧侶をしていたとも伝えられています。
油売りから大名に
道三が美濃国の当主となるまでの過程は、まさに下剋上を体現したものでした。
まず美濃守護代であった斎藤家の内紛に乗じて勢力を拡大しました。
その後、道三は美濃守護の土岐頼芸に取り入り、信頼を得ることに成功します。
しかし、道三は頼芸を意のままに操り、実質的に美濃国を支配するようになりました。
そして、ついには頼芸を追放し、自らが美濃国の新たな支配者として君臨することになったのです。
道三の娘、帰蝶
道三の娘である帰蝶(濃姫)は織田信長の正室です。
帰蝶は政略結婚により信長に嫁ぎましたが、単なる政略結婚にとどまらず、信長との間に深い絆を築いたとされています。
彼女は聡明で勇敢な女性として描かれることが多く、信長の政治や戦略に影響を与えたと言われています。
道三は娘を信長に嫁がせることで、尾張国の織田家と同盟関係を結び、美濃国の安定を図りました。
しかし、道三は単に帰蝶を道具として見ていたわけではなく、彼女の才能を高く評価していたとも言われています。
息子との対立
道三は息子の斎藤義龍と激しく対立していました。
義龍は、道三が土岐頼芸の子であるという疑いを抱き、道三を討つことを決意し1556年に長良川を挟んで激突しました。
これが「長良川の戦い」です。
義龍軍は17,500余名、対する道三軍は2,700余名と兵力差は圧倒的でした。
娘婿である織田信長は、道三救援のため出陣しましたが間に合わず、道三は討ち死にしました。
道三の居城であった「岐阜城」
岐阜城は元々「稲葉山城」と呼ばれ、道三が美濃国の実権を握る過程で本拠とした城です。
道三が長良川の戦いで敗死した後、信長が稲葉山城を攻略し、「井の口」と呼ばれていた地名を「岐阜」と改めたことから岐阜城と名前が改められました。
岐阜城は金華山山頂に位置し、最上階からは長良川や濃尾平野を一望できる絶景が広がります。
道三や信長が目にしていたであろう天守からの景色を見に行ってみてはいかがでしょうか。

斎藤道三の年表
- 1494年:山城(京都府南部)に生まれる(諸説あり)
- 1527年:土岐頼純を追放し、土岐頼芸を守護にする
- 1530年頃:長井家を乗っ取る
- 1538年:守護代斎藤家の家督を継ぎ、斎藤利政と名乗る
- 1542年:土岐頼芸を追放し、美濃国を乗っ取る
- 1548年:娘を織田信長に嫁がせる
- 1556年:嫡男の義龍との戦いで討ち死に