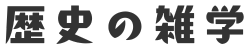龍造寺隆信は、戦国時代の九州の肥前国(佐賀・長崎)で活躍した戦国大名です。
数々の戦を経験し、武勇に優れたため「九州三強」の一人に数えられた人物でした。
この記事では
- 龍造寺隆信の出自
- 龍造寺隆信の強さの秘訣
- 龍造寺隆信の年表
などの雑学を歴史初心者にもわかりやすく解説します。
※諸説あるものや逸話が含まれます。
龍造寺隆信の雑学
めずらしい出自
隆信は、龍造寺氏の分家である水ヶ江龍造寺家の出身です。
龍造寺氏本家の後継者争いに巻き込まれたことで、一度は出家して僧となり、円月と名乗ります。
その後、少弐氏によって、父をはじめとする水ヶ江龍造寺家の一族は滅ぼされてしまいますが、隆信自身は僧であったことで生き残りました。
翌年、隆信の曾祖父である家兼の要請により、龍造寺家に戻り、龍造寺氏の家督を相続しました。
龍造寺家は曾祖父から曾孫への家督継承という、戦国時代でも稀な例を成功させたと言えます。
九州三強の一人
須古城を拠点とし卓越した軍事力と戦略で肥前国を中心に勢力を拡大、最盛期には五州二島の大領国を築きました。
- 肥前
- 肥後
- 筑前
- 筑後
- 豊前
- 壱岐島
- 対馬
これらの地域は現在の佐賀・長崎両県、福岡県の大半、熊本県の北半と大分県の一部を網羅します。
その広大な領土を称して「五州二島の大守」と呼ばれました。
また「九州三強の一人」とも呼ばれ、島津氏、大友氏と並び九州における三大勢力の一角を担っていました。
熊と呼ばれた理由
隆信は剛腕かつ冷酷な判断力を持つ武将として知られ、「肥前の熊」と恐れられました。
敵対する勢力に対しては容赦なく、その武勇と冷徹さから「熊」のような恐ろしさを感じさせたと言われています。
戦場においては非常に獰猛な戦いぶりで敵を圧倒するような力強さがあり、まるで「熊」が獲物を襲うかのようであったと伝えられています。
隆信の最後
1584年に、隆信率いる龍造寺軍と、有馬・島津連合軍による沖田畷の戦いが発生しました。
沖田畷は湿地帯となっており、龍造寺軍は不慣れな地形ゆえ、思うように戦うことが出来ませんでした。
逆に島津軍は地形を熟知していたため、龍造寺軍の側面を突く戦術を展開し、龍造寺軍は混乱の末総崩れとなりました。
そして隆信自身もこの合戦で討ち死にしました。
この戦いは戦国時代の九州における重要な転換点となった戦いであり、隆信の生涯を締めくくる悲劇的な戦いでもありました。
龍造寺隆信の年表
- 1529年:誕生
- 1536年:出家し寺僧となる
- 1545年:祖父、父が少弐氏に誅伐され筑後へ逃れる
- 1559年:少弐氏を滅亡させる
- 1578年:大友氏の領地に侵攻
- 1580年:筑前、筑後、肥後、豊前を掌握
- 1584年:沖田畷の戦いで討死