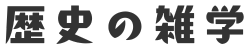今川義元は、戦国時代に活躍した戦国大名です。
現在の静岡県にあたる駿河・遠江を治め、政治・軍事において優れた手腕を発揮しました。
また、織田信長の天下統一にも深く関わる人物でもあります。
この記事では
- 今川義元が東海一の大名となるまでのエピソード
- 今川義元に訪れた悲劇
- 今川義元の年表
などの雑学を歴史初心者にもわかりやすく解説します。
※諸説あるものや逸話が含まれます。
今川義元の雑学
幼少期は僧侶として過ごす
今川義元には複数の兄がいたため、4~5歳の頃に出家して駿河国の善徳寺に入りました。
そこで後に今川義元の軍師的存在となる太原雪斎と出会い、当時における最先端の教育を受け、僧侶として修行を積みました。
この幼少期の経験が、大名になったのちも領国経営や外交の場で活かされることになり、今川義元は東海地方を代表する戦国大名になりました。
お家騒動を制し今川家当主に
義元が18歳の時に、兄であり今川家8代目当主でもある今川氏輝が急死します。
氏輝には子がなく、後継者が決まっていませんでした。
そのため今川家は次期当主を巡り、義元を当主に推すグループと、腹違いの兄弟である恵探を推すグループに分裂し、対立することになります。
最終的には「花倉の乱」が勃発し、義元勢力と恵探勢力の決戦が始まりました。
恵探は静岡県にある花倉城に籠城し、義元に対抗する戦法をとりました。
はじめは恵探側が優勢に戦いを進めましたが、義元は自身の師である太原雪斎を味方につけます。
雪斎が加わったことにより、戦の優位性は逆転し義元が花倉の乱を制しました。
義元は今川家の当主となり、戦国大名としての一歩を踏み出すことになりました。
公家文化を崇拝していた
義元は公家文化を好み、お歯黒や白粉化粧をするなど公家のような格好をしていたと言われています。
母が公家出身であったことから、幼い頃から公家文化に親しみ、和歌や蹴鞠などの教養を身につけたとも言われています。
桶狭間の戦いでの悲劇的な死
義元は隣国の尾張国(愛知県)を支配していた織田信秀(織田信長の父)の死を受け、1560年に約25,000もの大軍を率い、信秀の後を継いだ織田信長が治める尾張国に侵攻します。
義元は軍師である太原雪斎を病気で失っており、かつての勢いこそなかったものの、今川家の勢力は衰えておらず、次々と織田軍の城を攻略していきます。
織田信長の居城である「清州城」まであと一歩と迫ったところで、義元は「桶狭間」という場所で軍を止め休息をとります。
そんな中、突如として織田信長の奇襲部隊が現れ今川義元はあっけなく織田軍によって討ち取られてしまいました。
義元が討たれた結果、今川軍は撤退。その後有力な指導者が現れることなく今川家は衰退します。
逆にこの戦いで大大名である義元を討った織田信長は一躍名声を上げ、天下統一への第一歩を踏み出すのでした。
「海道一の弓取り」と称される
桶狭間の戦いで織田信長にあっけなく討ち取られたことや、公家文化を崇拝し文化人のイメージが強いことから、今川義元の大名・武将としての能力は低くみられがちです。
しかし、決してそんなことはありません。
今川義元は大名になった当初から、優れた外交手腕を発揮し北条家や武田家と同盟を結び、後継者争い直後の国内を安定させ、勢力拡大への体制を整えました。
尾張侵攻についても、結果的には織田信長が一枚上手ではありましたが、戦略としては順当なものだったと考えられます。
また義元を称する言葉として「海道一の弓取り」という言葉があります。
「海道」とは「東海道」のこと、「弓取り」とは「弓矢で戦う=武士」を転じて「国持大名」のことを指します。
すなわち、義元は「東海道で一番の大名である」と当時から高い評価を得ていたのです。
今川義元の年表
- 1519年:今川氏親の三男として生まれる
- 生年不詳:僧籍に入る(栴岳承芳と名乗る)
- 1536年 :花倉の乱に勝利し、今川家当主となる
- 1540年 :駿河・遠江の守護となる
- 1554年 :甲相駿三国同盟を締結する
- 1560年:桶狭間の戦いで織田信長に討たれる