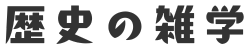佐竹義重は、戦国時代に活躍した戦国大名です。
現在の茨城県付近にあたる常陸国で勢力を拡大し、南の北条氏や北の伊達氏と争いました。
この記事では
- 佐竹義重が関東で恐れられた理由
- 佐竹義重の兜の秘密
- 佐竹義重の年表
などの雑学を歴史初心者にもわかりやすく解説します。
※諸説あるものや逸話が含まれます。
佐竹義重の雑学
「鬼義重」の異名を持つ
義重は戦場において常に先頭に立ち、自ら敵陣に切り込んでいく勇猛果敢な武将でした。
ある時には、7人の敵を一瞬で斬り伏せたという逸話も残っています。
その圧倒的な武力と敵を容赦なく打ち破る姿から「鬼義重」と恐れられるようになりました。
義重と戦うことを恐れた敵は、戦わずして降伏することもあったと言われています。
兜のトレードマークは「毛虫」
戦国時代の武将はそれぞれ個性ある甲冑を身に着けています。
特に個性が現れやすいのは兜についている「前立て」と呼ばれる飾りで、武将のトレードマークのようなものです。
前立てには縁起の良いものや、勝利を連想させるものが取付られました。
その中でも特に派手だったり、個性的な前立てがついた兜のことを「変わり兜」といいます。
※前立てだけでなく、兜自体が変わった形をしている場合も「変わり兜」と呼ばれます。
佐竹義重が身に着けた兜も、その「変わり兜」の一つです。
義重が戦場で身に着けた兜の前立てには「黒茶色の細長いモフモフ」が付けられていました。
その正体はなんと「毛虫」です。
義重が前立てに毛虫を採用した理由は諸説ありますが「毛虫は決して後ろに退かない」という習性にあやかり、佐竹家の不退転の決意を表したという説や、「毛虫は葉を食む」を転じて「敵の刃を食む」とという意味を込めたという説があります。
この毛虫型の前立は、長男の佐竹義宣にも引き継がれて、佐竹家のトレードマークとなりました。
強大な勢力相手にもうまく立ち回り、佐竹家を後世に残す
佐竹氏は常陸国を拠点に関東北部で勢力を拡大しました。
一方、南には相模国(現在の神奈川県)を中心に関東地方の大部分を支配していた「北条氏」がおり、
両者は互いの領土をめぐって、度々衝突を繰り返し対立していました。
また、戦国時代中盤になると、関西では豊臣秀吉が勢力を拡大し、天下統一を目指して関東の大名に対して豊臣家の支配下に入るよう要求します。
このような刻々と勢力図が変化する状況で、義重は豊臣家に従うことを決めます。
逆に、北条氏は豊臣家との徹底抗戦の構えをとったのでした。
そして、1590年に豊臣秀吉が北条氏を討伐するために「小田原征伐」を開始すると、義重は子の義宣と共に参陣します。
結果、豊臣秀吉が北条氏を下し北条氏は滅亡します。
逆に、小田原征伐に協力した佐竹氏は豊臣政権下で領地を治め続けることを許され、佐竹家を存続させることに成功しました。
敵を八の字に斬り裂く愛刀「八文字長義」
義重の愛刀として特に有名なのは、「八文字長義」です。
これは南北朝時代の備前長船(岡山県瀬戸内市)の刀工、長義によって作られた刀です。
義重が北条氏との戦いで使用し、敵の騎馬武者を兜ごと真っ二つに斬り捨てた際、その武者の体が馬の左右に「八の字」のように落下したことから、この名がついたと伝えられています。
佐竹義重の年表
- 1547年:誕生
- 1562年:家督相続
- 1564年:上杉謙信と共に出陣、小田城を攻略
- 1567年:白河城を攻略
- 1569年:小田氏治と手這坂で戦う
- 1570年:南奥に出陣
- 1574年:北条氏政と和睦
- 1575年:白河城が佐竹氏の手に落ちる
- 1582年:古河城を攻撃
- 1585年:伊達政宗と安積表で戦う
- 1590年:嫡男義宣が常陸を統一
- 1602年:隠居
- 1612年:死去