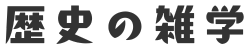最上義光は戦国時代に出羽国(山形県)を中心に活躍した大名です。
知略に長け、周囲の強大な勢力にも屈せず戦国時代を生き残りました。
一方で疑り深く、冷徹な一面もある人物でした。
この記事では
- 最上義光の人物像
- 最上義光と伊達政宗の関係
- 最上義光の年表
などの雑学を歴史初心者にもわかりやすく解説します。
※諸説あるものや逸話が含まれます。
最上義光の雑学
家族との確執から猜疑心が生まれる
義光は1546年に最上家第10代当主、最上義守の嫡男として山形城で生まれました。
父の義守は義光の能力を十分に評価しておらず、弟の義時をかわいがり後継者にしようと考えていたため、義光との対立を深めました。
結局、義光が家督を継ぎ11代当主になったものの、弟の義時とは激しい対立続き、最終的には義光が弟の義時を滅ぼすという悲劇的な結末を迎えました。
家督争いを制した義光は、その後の戦国時代において最上家を大きく発展させ、出羽国の有力大名としての地位を確立しますが、このような経験が義光に強い猜疑心や冷徹な一面をもたらすきっかけになったと言われています。
伊達政宗の叔父となる
義光は東北地方でも強い力をもっていた伊達家との関係改善を図るため、妹である義姫を伊達輝宗(伊達政宗の父)に嫁がせました。
義姫は後に戦国時代を代表する武将である「伊達政宗」を生み、義光は政宗の叔父にあたる存在になりました。
美しい娘の悲劇
義光と正室の間に生まれた駒姫は、とても美しいことで知られていました。
その評判を聞きつけた豊臣秀次(豊臣秀吉の養子で秀吉の後継者に指名されていた人物)の目に留まり、側室にほしいと言われます。
義光は何度も断りましたがいつまでも逆らい続けることもできず、側室として召されることになりました。
しかし、豊臣秀吉の実子「豊臣秀頼」が生まれると、秀次は秀吉の命令で切腹させられます。
このとき駒姫も連座して処刑されてしまいました。
当時、駒姫はまだ15歳という若さで、駒姫の死を義光は非常に悲しみました。
義光は駒姫の供養のために専称寺を建立し、専称寺には駒姫の肖像画が残されています。
最上川を整備し領国発展に貢献
義光は領内の開発にも力を入れ領国の経済発展に貢献しました。
特に最上川の治水工事に力を入れ、洪水被害の軽減や新田開発を推進し、農業生産の向上と領民の生活安定に繋がりました。
また、最上川の舟運を整備し商業の流通を促進しました。
義光の内政政策により最上領は経済的に大きく発展し、領国を安定させるための重要な要素でした。
最上義光の年表
- 1546年: 最上義守の嫡男として生まれる
- 1564年: 父・義守が隠居し家督を相続する
- 1570年: 天童頼澄を滅ぼし天童氏を傘下に収める
- 1578年: 上杉謙信の死後、上杉景勝と対立する
- 1582年: 織田信長に臣従する
- 1584年: 嫡男・義康を廃嫡する
- 1590年: 小田原征伐に参陣し所領を安堵される
- 1600年: 関ヶ原の戦いで東軍に与し戦功を挙げる
- 1601年: 出羽山形藩57万石の初代藩主となる
- 1614年: 大坂冬の陣に参陣する
- 1617年: 死去