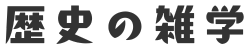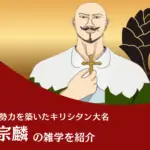三好長慶は戦国時代に活躍した大名です。
四国・近畿を中心に勢力を拡大し、一時は室町幕府の実権を掌握、織田信長に先駆けて天下人に近かった人物とも言われています。
この記事では
- 三好長慶が天下人の先駆けと呼ばれた理由
- 三好長慶が活躍したエピソード
- 三好長慶の年表
などの雑学を歴史初心者にもわかりやすく解説します。
※諸説あるものや逸話が含まれます。

さっそく三好長慶の素顔に迫るニャ!
三好長慶の雑学
天下人の先駆け
三好家はもともと阿波(徳島)の守護大名を務めた家系ですが、戦国時代に入り三好長慶が率いるようになると勢力を近畿地方にまで伸ばしていきました。
最盛期には、近畿地方の山城・大和・摂津・河内・和泉の他、阿波・淡路・讃岐・丹波・丹後・播磨東部を支配下に置き、室町幕府をも凌駕する権力を持ちました。
近年では織田信長に先駆けた天下人だとも言われ、再評価されつつあります。

織田信長の武力による勢力拡大とは対照的に、長慶は政治・外交面で手腕を発揮して勢力拡大していったニャ。長慶は寛大な性格で、近畿進出時も朝廷や幕府と積極的に争おうとはせず、和平の道を探っていたと言われているニャ。
日本の副王
長慶は一時期、室町幕府の権力をも抑えて、日本の政治を動かすようになりました。
この政治の実権が三好家にあった時期を「三好政権」と呼びました。
また一守護大名から日本を動かすほどの強大な権力を持つようになった長慶は「日本の副王」と称されるようになりました。
文化を重んじた人物
1560年に居城を芥川山城から飯盛山城に移してからは、政治、経済、文化の中心地として発展させました。
また連歌や茶の湯を奨励し、キリスト教の布教を許可するなど、文化面でも大きな功績を残しました。
飯盛山城では3日間にわたって連歌会を催し、千句もの連歌を詠んだ「飯盛千句」として記録が残っています。

長慶は戦乱の世であっても、安定した政治や文化の普及に努めるなど器量の大きい人物であったニャ。
不幸が重なった晩年
長慶は晩年、それまでの栄華とは対照的に不幸に見舞われ、三好家は衰退の一途を辿りました。
1560年代に入ると、長年長慶を支えてきた弟たちが相次いで死去し、さらに息子の義興も若くして世を去りました。
これらの不幸により長慶の心に深い傷を負い、とても政治を行えるような状態ではなくなっていきます。
また、追い打ちをかけるように策略家として名高い家臣の松永久秀の台頭を許し、次第に実権を奪われていきます。
そして1564年に長慶は失意のうちに病死しました。享年43歳という若さでした。
長慶の死後、三好家は急速に衰退し、やがて織田信長の近畿平定によって歴史の表舞台から姿を消しました。

これまでの長慶の活躍は、長慶個人のリーダーシップというよりも、優秀な弟や部下の存在があってこそのものだったニャ。
それだけに、頼れる存在を次々と失った長慶の失意は計り知れないものだったニャ。
芥川山城と飯盛城
1549年の江口の戦いで勝利した長慶は細川晴元を追放し、1553年に芥川山城を攻め落として自身の居城としました。
長慶は京都に入ることなく、この芥川山城から畿内を支配しました。
多くの文献や史料によって築城から廃城までの経緯が明らかになっている全国的にも珍しい城です。
※令和4年芥川山城跡は、国の史跡「芥川城跡」になりました。
1560年には、より畿内中央に近い飯盛城に拠点を移しました。
長慶が政権を握った期間は長くはありませんでしたが、この城を拠点に室町幕府の政治を動かし、首都のような場所となりました。

三好長慶の年表
- 1522年:阿波国で生まれる
- 1533年:父・三好元長が細川晴元によって自害させられる
- 1540年:細川晴元に仕える
- 1547年:江口の戦いで細川氏綱を破る
- 1549年:摂津国に進出し、本拠地とする
- 1550年:細川晴元を京都から追放する
- 1553年:将軍・足利義藤(後の義輝)を擁して京都に入る
- 1555年:畿内とその周辺をほぼ制圧する
- 1558年:足利義輝と対立し、京都から一時的に退却する
- 1560年:和泉国堺を拠点に勢力を回復する
- 1561年:再び京都に入る
- 1563年:嫡男の三好義興が急死する
- 1564年:自身も病死する