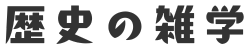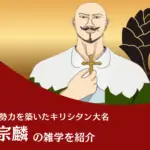酒井忠次は戦国時代に活躍した武将です。
徳川家の古参武将で「徳川四天王」の一人として数えられました。
文武に優れ、戦・政治・外交の場でバランスよく活躍した人物です。
この記事では
- 酒井忠次と徳川家康の関係
- 酒井忠次が活躍したエピソード
- 酒井忠次の年表
などの雑学を歴史初心者にもわかりやすく解説します。
※諸説あるものや逸話が含まれます。
酒井忠次の雑学
徳川四天王のリーダー格
忠次は徳川家康の父である松平広忠の時代から徳川家に仕えた最古参の武将です。
忠次は家康より15歳年上で、家康が幼少の頃から側近として仕えていました。
家康が今川家へ人質として送られた際には、忠次がお供をつとめ苦楽を共にしました。
家康から見たら忠次は家族にも等しい存在だったかもしれません。
このような信頼関係に加え、忠次は戦や政治の場でもしっかりと功績を残す優秀な武将であったため、
後の徳川四天王(酒井忠次・本多忠勝・井伊直政・榊原康政)の筆頭として名を残すことになりました。
家康を天下に導いた軍才
忠次は軍略に精通した武将で、数々の戦で勝利に貢献しています。
1556年の福谷城の戦いでは、織田信長の重臣で、織田軍の中でも突出した武勇を誇る柴田勝家率いる軍勢を相手に、籠城戦ではなく城外の野戦で勝利を収めています。
また、1575年に織田・徳川連合軍と武田軍が戦った「長篠の戦い」において、忠次は徳川軍の別働隊を率いて、武田軍が守る砦への奇襲を成功させました。
この作戦の成功は長篠城への補給路を確保し、武田軍の背後を突く重要な役割を果たしました。
忠次が軍議でこの奇襲作戦を織田信長に提案した際、信長は一度この提案を退けています。
しかし、軍議が終わったのち、信長は忠次に奇襲作戦を実行するよう密かに命を出しました。
優れた奇襲作戦であると認めたからこそ、情報漏洩を防ぐために信長は軍議であえて提案を退け、内密に命を出したとも言われています。
このように忠次は様々な戦で軍略で主君を助け、家康を天下に導いていきました。
酒井の太鼓
「酒井の太鼓」とは、1573年の「三方ヶ原の戦い」で徳川家康が武田信玄に大敗し、居城の浜松城へ逃げ帰った際に生まれた逸話です。
敗戦により兵士たちの士気が著しく低下する中、忠次は城の櫓に上がり、力強く太鼓を打ち鳴らしましたといいます。
この行動には2つの狙いがあり、1つは味方を鼓舞すること、もう1つは武田軍を牽制することでした。
太鼓の音は城内に活気を取り戻し、兵士たちの士気を高めました。
また、武田軍は浜松城に伏兵が潜んでいるのかもしれないと警戒し、浜松城への突撃をやめ撤収したと言われています。
この忠次の機転により、徳川軍は体勢を立て直す時間を得ることができました。
不遇の晩年
家康から信頼を得ていた忠次ですが、関係が悪化してしまう事件が起きます。
それは徳川家康の息子の信康が敵である武田家と内通しているという疑いが織田信長に伝えられたことがきっかけでした。
この時、忠次は信長の元へ弁明しに行きますが、十分な弁明が出来ず信康の疑いを晴らすことが出来ませんでした。
結果、家康は苦渋の決断で信康に切腹を命じました。
この事件以降、家康と忠次の関係にはひびが入り、酒井家に割り当てられる領地が減ったり、新参武将のほうが重用されるようになるなど、不遇な晩年を過ごしたと言われます。
しかし、それでもなお忠次の忠誠心が薄れることはなく、最後まで徳川家のために尽力しました。
酒井忠次の年表
- 1527年:三河国で生まれる
- 1542年頃:松平広忠(徳川家康の父)に仕える
- 1560年:桶狭間の戦いに参加する
- 1563年:三河一向一揆鎮圧に功績をあげる
- 1570年:姉川の戦いで奮戦する
- 1572年:三方ヶ原の戦いで殿軍を務める
- 1575年:長篠の戦いで武田勝頼の本陣を急襲する
- 1582年:本能寺の変後、徳川家康の伊賀越えを助ける
- 1584年:小牧・長久手の戦いに参加する
- 1590年:徳川家康の関東移封に伴い、下総国臼井藩1万石を与えられる
- 1596年:死去