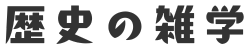真田昌幸は戦国時代に活躍した武将です。
真田家当主として、さまざまな大名に仕え軍才を奮ってきました。
この記事では
- 真田昌幸がとった戦国時代を生き残るための手腕
- 真田昌幸が戦国一の知将といわれる理由
- 真田昌幸の年表
などの雑学を歴史初心者にもわかりやすく解説します。
※諸説あるものや逸話が含まれます。
真田昌幸の雑学
人質でありながら武田信玄の側近に
真田昌幸は幼少の頃を武田家の人質として過ごしました。
真田家は弱小勢力で、生き残るためには武田家に従う必要があったからです。
当時、勢力同士が主従関係なる際は裏切りを防ぐために人質を送ることがよくありました。
しかし、昌幸は人質の身でありながらも武田信玄に才能を見出され、信玄の元で兵法などを学ぶことができました。
そして才能はすぐに開花し、人質としては異例の信玄の側近に登用されることになりました。
変幻自在の主君替えと一族を残すための戦略
昌幸は、その人生の中で何度も主君を変えた珍しい武将です。
幼少期は武田信玄に仕え、武田氏滅亡後は生き延びるために織田信長に従属しました。
本能寺の変で信長が亡くなった後は上杉景勝に従属、上杉家との関係が悪化すると北条氏直に従属しました。
さらに、北条家との関係が悪化すると徳川家康に、徳川家との関係が悪化すると豊臣秀吉に従属しました。
才能あふれる昌幸だからこそこのような世渡りが出来たのでしょう。
そして昌幸の真田家生き残り戦略は晩年にも光ります。
天下分け目の戦いとして有名な「関ヶ原の戦い」では、徳川家康率いる「東軍」と石田三成率いる「西軍」がぶつかりましたが、この時真田家は東軍、西軍に分裂することになります。
西軍には昌幸と息子の真田信繁(幸村)が、東軍にはもう一人の息子の信之が属しました。
東軍の信之は、父昌幸と弟の信繁に東軍に属すよう説得しますが、昌幸は拒否します。
この時昌幸が説得を拒否した理由は諸説ありますが、東軍西軍どちらが勝ったとしても一方の真田家は残るので一族を存続させることができるからという説もあります。
合戦の結果、西軍は敗れ昌幸と信繁は流罪となりますが、信之は徳川家の臣下として江戸時代まで生き抜きます。
そして、真田家は江戸時代以降、上田藩・松代藩を治める家として存続し続けました。
徳川軍を2度も手玉にとる
真田家と徳川家の関係が悪化すると、徳川家康は真田家を力で従わせようとします。
家康は昌幸に対して、真田家が治める領地の引き渡しを要求しますが当然昌幸はこれを拒否します。
怒った徳川家康は昌幸の居城「上田城」に7,000の軍勢で侵攻し「第一次上田合戦」が開戦しました。
兵数は徳川軍が真田軍を大きく上回り、真田軍は不利かと思われましたが、昌幸は上田城の構造と周囲の地形を巧みに利用し、徳川軍を追い返すことに成功します。

また、徳川家康の息子である秀忠が、関東から関ヶ原の戦いに向かう途中、38,000の軍勢で再度上田城を攻撃します。「第二次上田合戦」の開戦です。
この時、上田城には昌幸とその息子である信繁(幸村)が率いる2,500程の兵しか存在しませんでした。
秀忠は数万の兵力差があれば上田城をすぐに落とせると思っていましたが、昌幸の采配により少数の籠城戦で徳川軍を釘付けにすることに成功します。
結果、秀忠は関ヶ原の合戦に遅刻することになり、父家康の怒りを買ったのでした。
こうして、兵力に勝る徳川軍を2度も手玉にとった昌幸は、軍略の天才として後世に語り継がれることになりました。
九度山での最期
昌幸は関ヶ原の戦いの後、家康によって西軍に協力した罪で「九度山(和歌山県)」へ流罪となりました。
九度山での生活は昌幸にとって不遇なものでしたが、その地で静かに暮らし、時折息子たちに手紙を送って状況を伝えていたと言われています。
そして1611年に昌幸は65歳で病死し、生涯九度山を出ることはかないませんでした。
真田昌幸の年表
- 1547年: 真田幸隆の三男として生まれる(幼名:源五郎)
- 1553年: 武田信玄のもとへ人質として送られる
- 1574年: 父・幸隆が死去
- 1575年: 長篠の戦いで兄・信綱、昌輝が戦死し、真田家を継ぐ
- 1582年: 織田信長が本能寺の変で死去、武田家旧領を巡り織田家臣や北条氏と争う
- 1585年: 第一次上田合戦で徳川家康軍を撃退
- 1589年: 豊臣秀吉の命により沼田城を北条氏に明け渡す
- 1590年: 小田原征伐に従い、旧北条領の一部を与えられる
- 1600年: 関ヶ原の戦いで次男・幸村(信繁)と共に西軍に属し、上田城で徳川秀忠軍を足止め
- 1600年: 関ヶ原の戦い後、高野山へ流罪となる
- 1611年: 紀伊国九度山にて死去