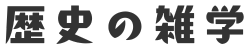大友宗麟は戦国時代に活躍した戦国大名で、九州北部に大勢力を築き上げた人物です。
またキリスト教を信仰するキリシタン大名としても有名です。
この記事では
- 大友宗麟とキリスト教の関係
- 大友宗麟が活躍したエピソード
- 大友宗麟の年表
などの雑学を歴史初心者にもわかりやすく解説します。
※諸説あるものや逸話が含まれます。

さっそく大友宗麟の素顔に迫っていくニャ!
大友宗麟の雑学
キリシタン大名の先駆け
大友宗麟はキリスト教を信仰する大名である通称「キリシタン大名」です。
1548年にフランシスコ・ザビエルが日本にキリスト教を広めるために来日すると、宗麟は自身が統治していた豊後国府内(現在の大分県)での布教活動を許可し、教会や学校の建設が進められました。
また、自らも洗礼を受けて「ドン・フランシスコ」という洗礼名を持っていました。

熱心なキリスト教徒になった宗麟だったけど、逆に神社仏閣を破壊するなど仏教を弾圧するような動きも見せたニャ。これが後に家臣団の離反や反乱を招く要因になったニャ。
海外との交流と領地発展
宗麟がキリスト教の布教を許したことは、大友家の発展にもつながりました。
南蛮(ポルトガルやスペイン)との交流が活発化し、貿易などが積極的に行われるようになります。
大友家は海外から最新の鉄砲や火薬を輸入して軍事力を強化して、周辺諸国への支配力を強化しました。
加えて、貿易都市として発展した府内には全国から商人や文化人が集るようになり、府内は政治的にも経済的にも大変豊かな国になったと言われます。
九州六カ国を支配
宗麟は最終的に豊後・豊前・筑前・筑後・肥前・肥後の北九州六カ国を支配下に置き、400年に及ぶ大友家の歴史の中で最大の領土を築き上げました。
その勢いで、宗麟は島津家が支配する南九州へと侵攻しますが、「耳川の戦い」で島津軍に大敗してしまいます。
その後、大友家は島津家により逆に侵略される立場となりピンチを迎えます。
そこで宗麟は天下統一目前の豊臣秀吉に助けを求めます。
秀吉はこれに応じ、九州征伐(島津家征伐)を実行、島津家を破り従わせることに成功します。
九州は秀吉の手によって平定され、大友家の領土は秀吉によって安堵されることになりました。

耳川の戦いで敗戦した結果、大友家が統治していた各地で反乱が起きたことで大友家の支配力が急速に低下したニャ。
島津家はこのチャンスを逃さず、大友家の領地に侵攻することになったニャ。
宗麟の最後
宗麟の最後は病死です。
宗麟の要請で豊臣秀吉の九州征伐(島津家征伐)が行われている最中、宗麟は病を患ってしまいました。
病気はチフスであったとされるのが有力説です。
島津家が豊臣軍に降伏する直前に58歳で亡くなったと言われています。
大友宗麟の年表
- 1530年: 大友義鑑の嫡男として生まれる(幼名:塩法師)
- 1550年: 父・義鑑が家臣に殺害され家督を継ぐ
- 1551年: 府内(現在の大分市)にフランシスコ・ザビエルを招き、キリスト教布教を許可
- 1557年: 豊後国をほぼ統一
- 1562年: 筑前国の立花鑑載を滅ぼす
- 1569年: 毛利元就の侵攻を受けるが撃退
- 1573年: 長男に家督を譲る
- 1576年: 日向国に進出
- 1578年: 耳川の戦いで島津氏に大敗
- 1586年: 島津氏の侵攻を受け、豊臣秀吉に救援を要請
- 1587年: 豊臣秀吉の九州征伐の最中に病死