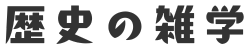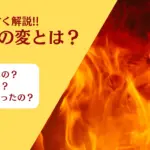島津義弘は戦国時代に主に九州南部で活躍した武将です。
非常に勇猛な武将で、戦いに関する様々な伝説を残しました。
この記事では
- 島津義弘が国内外から恐れられた理由
- 島津義弘が関ヶ原の合戦で残した伝説
- 島津義弘の年表
などの雑学を歴史初心者にもわかりやすく解説します。
※諸説あるものや逸話が含まれます。

今日は猛将「島津義弘」の素顔に迫るにゃ!
島津義弘の雑学を紹介
「鬼島津」として恐れられる
島津義弘は生涯で数多くの戦に出陣し、常に最前線で指揮を執りました。
その勇猛果敢な戦いぶりから「鬼島津」という異名で呼ばれるようになり、敵味方問わず恐れられていました。
特に、豊臣秀吉が行った朝鮮出兵に参加した際は、敵の明軍から「鬼石曼子(グイシーマンズ)」と恐れられたことが、この異名がついた理由のひとつになっているとも言われています。

戦国時代には他にも「鬼」の異名が付けられた武将がたくさんいるにゃ!
以下のページもチェックしてみてにゃ!
九州の桶狭間
義弘が率いる島津軍と伊東義祐が率いる伊東軍が激突した「木崎原の戦い」では、島津軍が300、伊東軍が3,000と兵力に大きな差がありました。
数の上では、圧倒的に島津軍が不利ですが、最終的に島津軍が勝利することになります。
その要因は島津軍がとった戦略にあります。
島津軍はおとりと伏兵を巧みに使い分け、伊東軍を各個撃破することに成功しました。
この戦法は後に「釣り野伏せ」と呼ばれ、島津家お得意の戦法になります。
また、この戦いは少数で大軍を打ち破ったという状況が、「桶狭間の戦い(織田信長が少数の兵で今川家の大軍を奇襲し、今川義元を討ち取った戦い)」と似ているとして、「九州の桶狭間」と呼ばれることがあります。

島津義弘は武力だけではなく、知略にも優れた武将だったニャ。
島津の退き口
徳川家康率いる東軍と石田三成率いる西軍が戦った「関ヶ原の合戦」において島津軍は西軍として参戦します。
西軍の敗戦が濃厚になると義弘は島津家を残すために戦場から退却すること決断します。
しかし、周りは敵だらけで退却口はもはやありませんでした。
ここで義弘は思い切った決断をします。なんと徳川本陣を突破して東軍側の退却口から脱出するというのです。
この時すでに島津軍は300人程度しか残っていませんでしたが、義弘は軍を率いて徳川本陣に突っ込みます。
当然敵側はこれを阻もうとしますが、島津軍の勢いを止めることは出来ませんでした。
この退却戦は「島津の退き口」と呼ばれ、義弘の決断力と島津家の武勇を示す出来事として語り継がれています。

この作戦では義弘を逃がすために多くの島津軍の将兵が犠牲になったニャ。
でも義弘が鹿児島に帰ることができたおかげで、関ヶ原合戦後の島津家と徳川家の和平交渉を対等に進められることができ、島津家の存続につながったニャ。
島津義弘の年表
- 1535年: 島津貴久の次男として生まれる(幼名:又三郎)
- 1554年: 初陣を飾る
- 1572年: 「木崎原の戦い」で伊東軍を破る
- 1578年: 「耳川の戦い」で大友軍を破る
- 1584年: 「沖田畷の戦い」で龍造寺隆信を討ち取る
- 1586年: 豊臣秀吉の九州征伐軍と戦う
- 1587年: 降伏し、豊臣家に従う
- 1592年: 「文禄の役(第1回朝鮮出兵)」に従軍、朝鮮で奮戦
- 1597年: 「慶長の役(第2回朝鮮出兵)に従軍、明の大軍を破る功績を挙げる
- 1600年: 関ヶ原の戦いで西軍に協力するも、西軍敗北を受け薩摩へ帰国
- 1619年: 鹿児島で死去