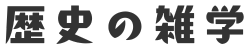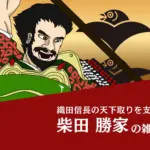加藤清正は戦国時代に活躍した武将です。
豊臣秀吉の家臣として戦で活躍したほか、有名な「熊本城」を建設した人物としても知られます。
この記事では
- 加藤清正と豊臣秀吉との関係
- 加藤清正と熊本城の関係
- 加藤清正の年表
などの雑学を歴史初心者にもわかりやすく解説します。
※諸説あるものや逸話が含まれます。
加藤清正の雑学
豊臣秀吉とは親戚関係
加藤清正と豊臣秀吉と親戚関係にあたります。
※それぞれの母が「いとこ」関係となるため、清正と秀吉は「はとこ」にあたります。
このような背景により、清正は幼い頃から豊臣秀吉に仕えていました。
加えて、清正は武芸に優れており、秀吉に対する忠誠心も高かったため、秀吉から気に入られ重臣として活躍することになりました。
「賤ヶ岳の七本槍」の一人

豊臣秀吉が柴田勝家を破った合戦「賤ヶ岳の戦い」で、特に武功を上げた豊臣軍の7人の武将たちのことを「賤ヶ岳の七本槍」と呼びます。
清正自身もこの戦で武功を挙げ、「賤ヶ岳の七本槍」の一人として数えられました。
これにより、清正を含めた武将たちが秀吉の側近として重用されることになり、以降様々な戦いや政治の場で活躍していくことになりました。
清正の他に、七本槍に数えられる武将は以下の通りです。
- 福島正則
- 加藤嘉明
- 脇坂安治
- 平野長泰
- 糟屋武則
- 片桐且元
「熊本城」の生みの親

清正は熊本県を代表する観光地「熊本城」を建設した人物です。
熊本城は1607年ごろに完成しました。
敵の侵入を防ぐため、下部は緩やかで上部になるほど急峻になる独特な石垣「武者返し」が備えられ、この石垣は「清正流石垣」とも呼ばれました。
他にも多重の堀・櫓・門を配置して敵を迷わせる複雑な構造にしたり、水路や兵糧庫を多数備え長期間の籠城戦にも耐えられる作りになっていました。
この熊本城のすごさが証明されるのは建設されてから約270年後、明治時代に入ってからになります。
1877年に西郷隆盛が明治政府に反旗を翻したことによって発生した「西南戦争」において、西郷隆盛は数万の兵を率いて熊本城に攻め込みます。
この時、熊本城には数千の政府軍しかいませんでしたが、西郷軍は熊本城の武者返しに侵攻阻まれ苦戦を強いられます。
西郷隆盛は兵糧攻めに切り替えますが、これも熊本城に十分な水と食料が蓄えられていたため失敗してしまいます。
結局、西郷隆盛は熊本城を落とすことは出来ませんでした。
この出来事により、熊本城を建設した加藤清正は後世の人々に評価され、「築城名手」として称えられることになったのです。

清正の虎退治伝説

清正の武勇を象徴する逸話として「虎退治」の伝説が残されています。
このエピソードが生まれたのは、豊臣秀吉が天下統一後に行った「朝鮮出兵」においてです。
清正もこの朝鮮出兵に参加しましたが、現地で豊臣軍が虎に襲われるという事件があったため、自ら槍を持ち虎を退治したと言われています。
ただし、この出来事を明確に記した資料は存在せず、「清正が虎を退治したのは主君の豊臣秀吉が虎肉を食べたがったから」「清正は槍ではなく鉄砲を使って退治した」などいくつかの説があります。
地震加藤

歌舞伎や落語において「地震加藤」という逸話が語られる場面があります。
これは、秀吉の勘気を被り謹慎を命じられていた清正が伏見大地震発生の際に、誰よりも早く秀吉の安否を気づかって伏見城へ駆けつけ、動けない秀吉を背負って避難させたという物語です。
この忠義心に秀吉は深く感動し、清正の謹慎を解いたとされます。
史実とは異なる点も指摘されますが、清正の勇敢さと秀吉への忠誠心を象徴する逸話として語り継がれています。
加藤清正の年表
- 1562年:尾張国愛知郡中村(現在の名古屋市中村区)に生まれる
- 1576年:織田信長に小姓として仕える
- 1582年:本能寺の変で信長が死去
- 1583年:賤ヶ岳の戦いで武功を挙げ、3000石を与えられる
- 1584年:小牧・長久手の戦いに従軍
- 1588年:肥後国北半分の領主となる(19万5千石)
- 1592年:文禄の役で朝鮮に渡り、各地で活躍
- 1597年:慶長の役にも従軍、蔚山城の戦いで奮戦
- 1600年:関ヶ原の戦いでは東軍に与し、戦功をあげる
- 1601年:肥後熊本藩52万石の初代藩主となる
- 1611年:京都で死去