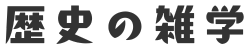伊達政宗は戦国時代に東北地方を中心に活躍した人物です。
持前のカリスマ性と先見の明で戦国時代を生き抜き、江戸時代の幕開けを支えました。
この記事では
- 伊達政宗の人物像
- 伊達政宗のカリスマ性が光るエピソード
- 伊達政宗の年表
などの雑学を歴史初心者の方にもわかりやすく紹介します。
※所説あるものや逸話が含まれます。
伊達政宗の雑学

隻眼の武将
政宗は、幼い頃に患った疱瘡(天然痘のこと)により右目を失明しました。
しかし、隻眼のハンデよりも政宗のカリスマ性が上回り、隻眼の武将はいつしか「独眼竜」という異名を持つことになりました。
この異名は、隻眼の龍という意味で、その勇猛な姿から人々を畏怖させたと言われています。
ちなみに戦国時代~江戸初期の隻眼の武将は他に「山本勘助(武田信玄の軍師)」「柳生十兵衛(剣豪)」がいます。
先代にも「政宗」がいた
政宗の幼名は梵天丸といいました。
これは、仏教における梵天に由来し、天下を取るようにとの願いが込められていたと言われています。
また、11歳で元服し、父・伊達輝宗より「政宗」という名前を授けられました。
この名前は、伊達家の中興の祖といわれた9代目当主・伊達政宗にあやかって名付けられたものです。
同じ名前なので少しややこしいですね。
父・輝宗は、息子が伊達家を再び興隆させるようにとの願いを込めて「政宗」という名前を与えたと考えられます。
伊達政宗の名前には、父の願いや伊達家への期待が込められていたと言えるでしょう。
母の愛情を受けられなかった
幼少期に右目を失明したことをきっかけに、実の母から嫌われていました。
母親は政宗よりも次男の小次郎を大変かわいがっていました。
小次郎を伊達家の跡継ぎにするため、政宗に毒を盛って殺害しようとする事件があったほどです。
政宗はその際、激しい腹痛に襲われましたが一命を取り留めました。
このような事件があっても、政宗は母親を処断することはせず、弟の小次郎のみを手討ちにすることで混乱を治めました。
世渡り上手
1590年に天下統一目前の豊臣秀吉から、小田原征伐(北条氏征伐)に参陣するよう命令がありました。
しかし、政宗は奥州仕置(奥州の戦乱を平定する)を優先を理由に、参陣を渋っていました。
最終的には小田原に参陣するものの、遅参となり秀吉の怒りを買うことになります。
秀吉は遅参した政宗に出頭を命じ、政宗はそれに応じますが、なんと政宗は死装束(白装束)で秀吉の前に現れ、堂々とした態度で弁明したといいます。
秀吉はそんな政宗の度胸に感心し、遅参の罪を許したと言われています。
自身の命がかかっている状況でこのような機転の利いたパフォーマンスを行い、秀吉の心をつかむことができることから、政宗のカリスマ性を感じ取ることができます。
グローバル大名
政宗は海外外交も積極的に行っていました。
1613年には、支倉常長をヨーロッパに派遣し、スペインやローマとの間に貿易関係を築こうとしました。
当時の国際情勢や宗教的背景から目的を達成することはできませんでしたが、支倉常長が日本人として初めて太平洋と大西洋を横断し、ヨーロッパに渡航したことは、日本の歴史上重要な出来事として評価されています。
これは、日本の戦国時代の終結と徳川幕府による新たな秩序形成という転換期において、伊達政宗が国際的な視野を持っていたことを表しています。
このような先進的な取り組みは仙台藩を豊かな藩へと成長させ、現在においても東北随一の都市として栄える礎になったと言えます。
伊達政宗の生き様を体感「みちのく伊達政宗歴史館」
日本三景の松島で有名な宮城県宮城郡松島町にある「みちのく伊達政宗歴史館」は伊達政宗の生涯と活躍を200体余りの等身大人形と25の名場面で再現・展示している観光施設です。
人形は1体1体躍動感があり、特に合戦を再現した等身大ジオラマは迫力満点です。
また、伊達政宗の兜や甲冑を身に着けて写真撮影できる有料サービスや、戦国時代に関わるグッズを揃えたショップがあり、思い出も残せる人気の観光スポットです。

伊達政宗の年表
- 1567年:出羽国(現在の山形県)で生まれる
- 1577年:元服し、藤次郎政宗と名乗る
- 1581年:初陣を飾る
- 1584年:家督を継ぎ当主となる
- 1585年:人取橋の戦いで、蘆名・佐竹連合軍を破る
- 1589年:摺上原の戦いで蘆名義広を破り、奥州の覇者となる
- 1590年:小田原征伐に参陣後、豊臣秀吉に従属する
- 1592年:文禄の役(朝鮮出兵)に参加
- 1600年:関ケ原の戦いで東軍側で参戦
- 1601年:仙台藩初代藩主となる
- 1604年:仙台城を築城
- 1613年:支倉常長をヨーロッパへ派遣
- 1614年:大坂冬の陣に参加
- 1615年:大坂夏の陣に参加
- 1636年:死去