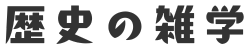長宗我部元親は戦国時代に土佐国(高知県)で活躍した大名です。
一代で四国制覇を成し遂げ、長宗我部家の全盛期を築き上げたことから「土佐の出来人」と称されました。
この記事では
- 長宗我部元親の人物像
- 長宗我部元親と戦国時代の人々との関係
- 長宗我部元親の年表
などの雑学を歴史初心者の方にもわかりやすく紹介します。
※所説あるものや逸話が含まれます。
長宗我部元親の人生
長宗我部元親は、土佐国(高知県)の戦国大名で、四国統一を成し遂げた武将です。
幼少の頃は「姫若子」と呼ばれるほどおとなしい少年でしたが、初陣で武勇を示し「鬼若子」と称されるようになりました。
その後、土佐国を統一すると、その勢いは止まらず10年間の間に阿波(徳島)、讃岐(香川)、伊予(愛媛)を次々と制圧し、ついには四国統一を成し遂げます。
しかし、その直後に豊臣秀吉の四国攻めが始まり、元親は敗北。
それまでに制圧した土地は没収され土佐一国のみを領有することが許されました。
四国統一の夢は数カ月で崩れてしまいました。
長宗我部元親の雑学
領民思いの大名
元親は、領民への思いやりを大切にした大名でした。
土佐国統一後、元親は善政を敷き積極的に新田開発や治水事業を行い、領民の生活向上に努めました。
また、飢饉や災害が発生した際は自ら陣頭指揮を執り、救援活動を行ったと言われています。
文化人との交流
戦国時代は戦だけでなく、お茶や能などの文化的な素養もステータスの一つでした。
元親も例に漏れず、文化人との交流を積極的に行っていました。
特に、連歌を好んでおり、自ら連歌会を催したり、他の連歌師に歌を贈ったりしたと言います。
また、茶人としても知られ、千利休とも交流があったと言われています。
短気な一面があった
元親は普段は温厚な人物でしたが、戦場では短気になる一面がありました。
敵の挑発に乗ってしまい、窮地に陥ることがあったと言われています。
しかし、その短気な性格が、時には家臣たちの奮起を促し、勝利に繋がったこともありました。
海戦が苦手だった
元親は、陸戦では卓越した才能を発揮しましたが、海戦には苦手意識を持っていたと言われています。
実際、四国統一戦においては海戦で苦戦したことが原因で、四国統一の遅延に繋がったとも言われています。
秀吉への複雑な感情
元親は、豊臣秀吉に対して、複雑な感情を抱いていました。
秀吉の才能を認めつつも、その強大な力に脅威を感じていたと言います。
四国攻めでの秀吉との戦いに敗れた後、元親は秀吉に従い、小田原征伐や知文禄の役(朝鮮出兵)にも従軍しますが、その心中は複雑だったことでしょう。
長宗我部氏に関する資料を多数所蔵する「高知県立歴史民俗資料館」
高知県南国市にある「高知県立歴史民俗資料館」には長宗我部展示室があり、長宗我部氏や岡豊城跡に関する資料が展示されています。
展示内には阿波・中富川合戦時の長宗我部軍本陣が再現されているので、戦国時代の雰囲気を体感できるスポットです。

長宗我部元親の年表
- 1539年:土佐国(高知県)に生まれる
- 1560年:初陣で武功をあげ、「鬼若子」と称される
- 1560年:長宗我部家の家督を継ぐ
- 1575年:四万十川の戦いに勝利し、土佐国を統一
- 1582年:中富川の戦いで三好家を破り、阿波国を支配
- 1585年:四国統一を果たす
- 1585年:豊臣秀吉の四国攻めに敗北。領地が土佐一国となる
- 1590年:豊臣秀吉の小田原征伐(北条氏征伐)に参加
- 1591年:浦戸城を築城し栄えさせる
- 1592年:文禄の役(朝鮮出兵)に参加
- 1599年:死去