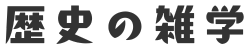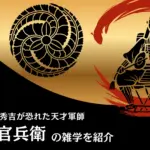山本勘助は戦国時代の武将で武田信玄に軍師として仕えました。
記録が少なくその生涯は謎に包まれており、実在していなかったといわれる説もあります。
この記事では
- 山本勘助の人物像
- 山本勘助が活躍したエピソード
- 山本勘助の年表
などの雑学を歴史初心者にもわかりやすく解説します。
※諸説あるものや逸話が含まれます。
山本勘助の雑学
勘助は実在した?
山本勘助は長い間、有力な記録がなく架空の人物であると考えられていました。
しかし、近年発見された書状などから、実在した人物である可能性が非常に高くなりました。
武田晴信(信玄)の書状に「山本菅助」の名が記されており、武田信玄の重要な家臣であったことが確認されています。
書状で確認できるのは「山本菅助」という名前で、一般的に知られる「山本勘助」と同一人物であるかについては見解が分かれていますが、少なくとも「ヤマモトカンスケ」という人物が存在したと言えます。
その生涯については不明な点が多く、謎に包まれた人物です。
大きなハンディキャップ
勘助は片目が見えず、片足も不自由だったとされています。
また色黒で醜男であったとも言われており、今川義元は勘助の容姿を嫌い召し抱えようとはしなかったという逸話もあります。
このような容姿故、どの大名にも相手にされなかった勘助ですが、武田信玄だけはその才能を見抜き、自身の軍師として迎え入れました。
勘助もまた、信玄の期待に応えて数々の戦で武田軍を勝利に導きました。
勘助と同じく、片目の見えない武将として伊達政宗があげられます。
よければ伊達政宗の雑学もチェックしてみてください。
キツツキ戦法
武田家の軍師となった勘助は、第四次川中島の戦いの時に奇策「啄木鳥戦法」を考案し、武田軍が上杉軍に対して用いたことで知られています。
この戦法は、軍を二手に分け、一方の部隊が敵軍を挑発して攻撃を仕掛け、敵軍がそれに気を取られている隙に、もう一方の部隊が背後から攻撃を仕掛けるという挟み撃ちの戦術です。
キツツキが木をつついて隠れている虫を驚かせて捕らえる様子から名付けられました。
しかし、上杉謙信が一枚上手で、この戦法は見破られてしまい、逆に武田軍は窮地に陥りました。
そしてこの時に勘助も命を落としたと言われています。
結果的にこの戦法は失敗に終わってしまったものの、自然から着想を得て斬新な戦法を生み出す勘助は軍師としてとても優れた人物でした。
優れた築城術
勘助は単に美しい城を築くだけでなく、実際の戦闘で敵の攻撃を防ぎ、味方が有利に戦えるような実戦的な城を築きました。
信濃(長野県)にある高遠城や海津城は勘助によって築かれたと言われています。
築城するにあたって、敵の戦力や周辺の地形、気候などを徹底的に調査し分析しました。勘助の築いた城はいずれも防御に優れ、武田軍の勝利に貢献しました。
山本勘助の年表
※山本勘助の年表は、生年を含めて諸説あり、はっきりとしたことは分かっていません。
- 1493年~1500年頃:三河国(愛知県)または駿河国(静岡県)に生まれる
- 1543年:武田家に仕官する
- 1544年:信濃国諏訪郡へ侵攻し平定する
- 1548年:上田原の戦いに参加
- 1561年:第四次川中島の戦いで戦死